「勉強したい気持ちはあるけど、時間がない」
そんな悩みを抱える社会人は少なくありません。
でも、続けている人たちは“やる気がある”からじゃなく、“仕組み”をつくっているから継続できているんです。
「時間がない」悩みに効く名著。人生は有限だと理解したうえで、“すべきこと”の選び方を見直す視点が得られます。完璧主義からの脱却にもつながる一冊。
この記事では、「勉強の時間をどう確保するか」に悩む社会人に向けて、今日から始められる5つのステップをご紹介します。
STEP1|まずは現状を見える化しよう
最初にやることは、「自分が今、何に時間を使っているか」を把握すること。
スマホのスクリーンタイム、1日の行動記録、1週間の生活スケジュールなど、ざっくりでも可視化してみましょう。
「仕事終わりはついダラダラSNSを見てしまう」
「テレビをなんとなくつけっぱなしにしている」
そんな“無意識の時間”が見えてくるはずです。
STEP2|目的と優先順位を明確にする
次に、「なぜ勉強したいのか」「どこまでやりたいのか」を明確にしましょう。
目的がはっきりしていないと、ちょっと忙しくなるとすぐに後回しになってしまいます。
例:
- 昇進のために資格を取りたい
- 英語を話せるようになって海外の仕事に挑戦したい
- 新しい知識を得て、仕事の幅を広げたい
目的が決まれば、「今日は何をやればいいか」がクリアになります。
STEP3|やめる/減らすことを決める(Stop)
時間は「増やす」のではなく「取り戻す」ものです。
やめられる習慣を1つだけでも見直してみましょう。
たとえば:
- SNSを30分減らす
- 通勤中のゲームをやめて音声学習に変える
- 朝起きてすぐのスマホチェックをやめて5分の読書へ
何かを削ることで、学びの時間が自然と生まれます。
STEP4|スキマ時間を学び時間に入れ替える(Swap)
「まとまった時間を作らないと勉強できない」
そう思いがちですが、実は細切れの時間でも十分効果があります。
- 通勤中:Podcastや音声講座を聴く
- 昼休み:10分で記事を読む
- 就寝前:その日学んだことを1行メモする
1日10分でも、1週間で70分。1か月で4時間以上です。
無理なく続けるコツは「小さく始めること」です。
STEP5|学びを習慣に落とし込む(Schedule)
毎日の中に、あらかじめ「学ぶ時間」を組み込んでしまいましょう。
ルーティンにしてしまえば、迷わずに続けられます。
おすすめは「既にある習慣にくっつける」こと。
- 朝コーヒーを飲む時間に英単語を3つ見る
- お風呂の後に動画講義を10分観る
- 土曜の午前中はカフェで1時間だけ勉強する
「時間があるかどうか」ではなく、「いつ、どこでやるか」を決めることで継続のハードルが下がります。
【それでもできなかったときは?】
完璧にやろうとしなくて大丈夫です。
できなかった日は「今日の行動に何があったか」を軽く振り返り、翌日に“微調整”すればOK。
- なぜできなかったか?(疲れた、時間が取れなかった)
- どうすれば同じ失敗を防げるか?(朝に前倒す、ハードルを下げる)
むしろ「失敗したこと」こそ、仕組みを見直すチャンスです。
「やる気に頼らない仕組み」を育てていく意識があれば、学びは自然と続きます。
【まとめ】
- 時間がない社会人こそ、“やる気”ではなく“仕組み”を使おう
- 現状の可視化 → 目的設定 → 時間の再設計 → 習慣化がポイント
- 完璧を求めず、小さく改善しながら継続しよう
「勉強できる人」とは、やる気に満ちた人ではなく、学びを生活の中に自然に組み込めている人です。
明日から、あなたの暮らしにも小さな“学びの仕組み”を取り入れてみてください。
“やる気”より“仕組み”。社会人が学びを続ける時間の作り方
「勉強したい気持ちはあるけど、時間がない」
そんな悩みを抱える社会人は少なくありません。
でも、続けている人たちは“やる気がある”からじゃなく、“仕組み”をつくっているから継続できているんです。
この記事では、「勉強の時間をどう確保するか」に悩む社会人に向けて、今日から始められる5つのステップをご紹介します。
STEP1|まずは現状を見える化しよう
最初にやることは、「自分が今、何に時間を使っているか」を把握すること。
スマホのスクリーンタイム、1日の行動記録、1週間の生活スケジュールなど、ざっくりでも可視化してみましょう。
「仕事終わりはついダラダラSNSを見てしまう」
「テレビをなんとなくつけっぱなしにしている」
そんな“無意識の時間”が見えてくるはずです。
STEP2|目的と優先順位を明確にする
次に、「なぜ勉強したいのか」「どこまでやりたいのか」を明確にしましょう。
目的がはっきりしていないと、ちょっと忙しくなるとすぐに後回しになってしまいます。
例:
- 昇進のために資格を取りたい
- 英語を話せるようになって海外の仕事に挑戦したい
- 新しい知識を得て、仕事の幅を広げたい
目的が決まれば、「今日は何をやればいいか」がクリアになります。
STEP3|やめる/減らすことを決める(Stop)
時間は「増やす」のではなく「取り戻す」ものです。
やめられる習慣を1つだけでも見直してみましょう。
たとえば:
- SNSを30分減らす
- 通勤中のゲームをやめて音声学習に変える
- 朝起きてすぐのスマホチェックをやめて5分の読書へ
何かを削ることで、学びの時間が自然と生まれます。
STEP4|スキマ時間を学び時間に入れ替える(Swap)
「まとまった時間を作らないと勉強できない」
そう思いがちですが、実は細切れの時間でも十分効果があります。
- 通勤中:Podcastや音声講座を聴く
- 昼休み:10分で記事を読む
- 就寝前:その日学んだことを1行メモする
1日10分でも、1週間で70分。1か月で4時間以上です。
無理なく続けるコツは「小さく始めること」です。
STEP5|学びを習慣に落とし込む(Schedule)
毎日の中に、あらかじめ「学ぶ時間」を組み込んでしまいましょう。
ルーティンにしてしまえば、迷わずに続けられます。
おすすめは「既にある習慣にくっつける」こと。
- 朝コーヒーを飲む時間に英単語を3つ見る
- お風呂の後に動画講義を10分観る
- 土曜の午前中はカフェで1時間だけ勉強する
「時間があるかどうか」ではなく、「いつ、どこでやるか」を決めることで継続のハードルが下がります。
【それでもできなかったときは?】
完璧にやろうとしなくて大丈夫です。
できなかった日は「今日の行動に何があったか」を軽く振り返り、翌日に“微調整”すればOK。
- なぜできなかったか?(疲れた、時間が取れなかった)
- どうすれば同じ失敗を防げるか?(朝に前倒す、ハードルを下げる)
むしろ「失敗したこと」こそ、仕組みを見直すチャンスです。
「やる気に頼らない仕組み」を育てていく意識があれば、学びは自然と続きます。
【まとめ】
- 時間がない社会人こそ、“やる気”ではなく“仕組み”を使おう
- 現状の可視化 → 目的設定 → 時間の再設計 → 習慣化がポイント
- 完璧を求めず、小さく改善しながら継続しよう
「勉強できる人」とは、やる気に満ちた人ではなく、学びを生活の中に自然に組み込めている人です。
明日から、あなたの暮らしにも小さな“学びの仕組み”を取り入れてみてください。
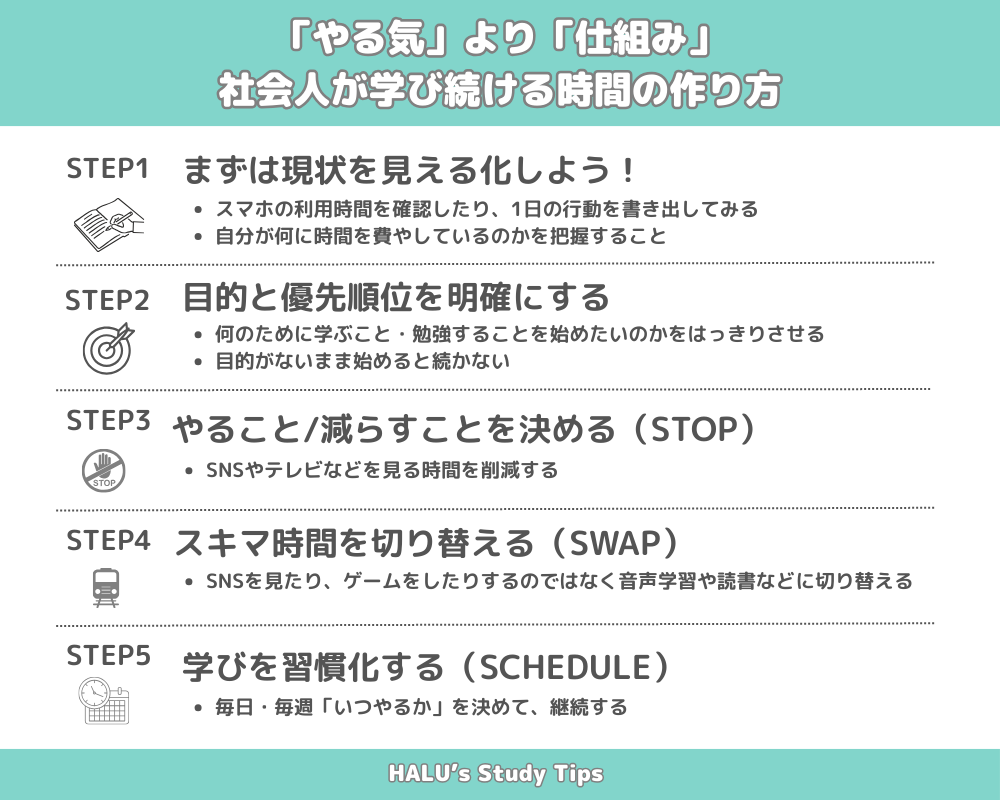
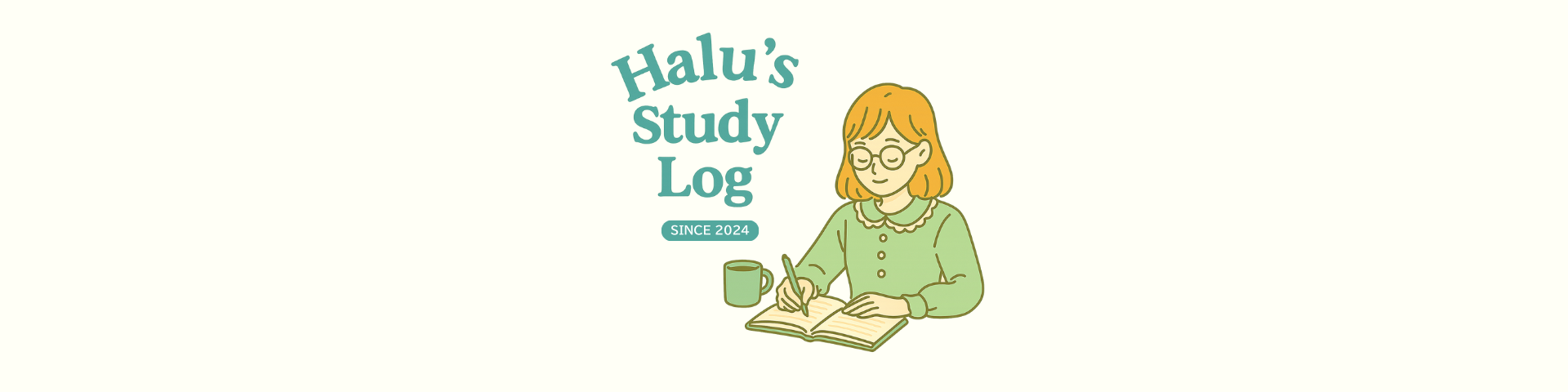


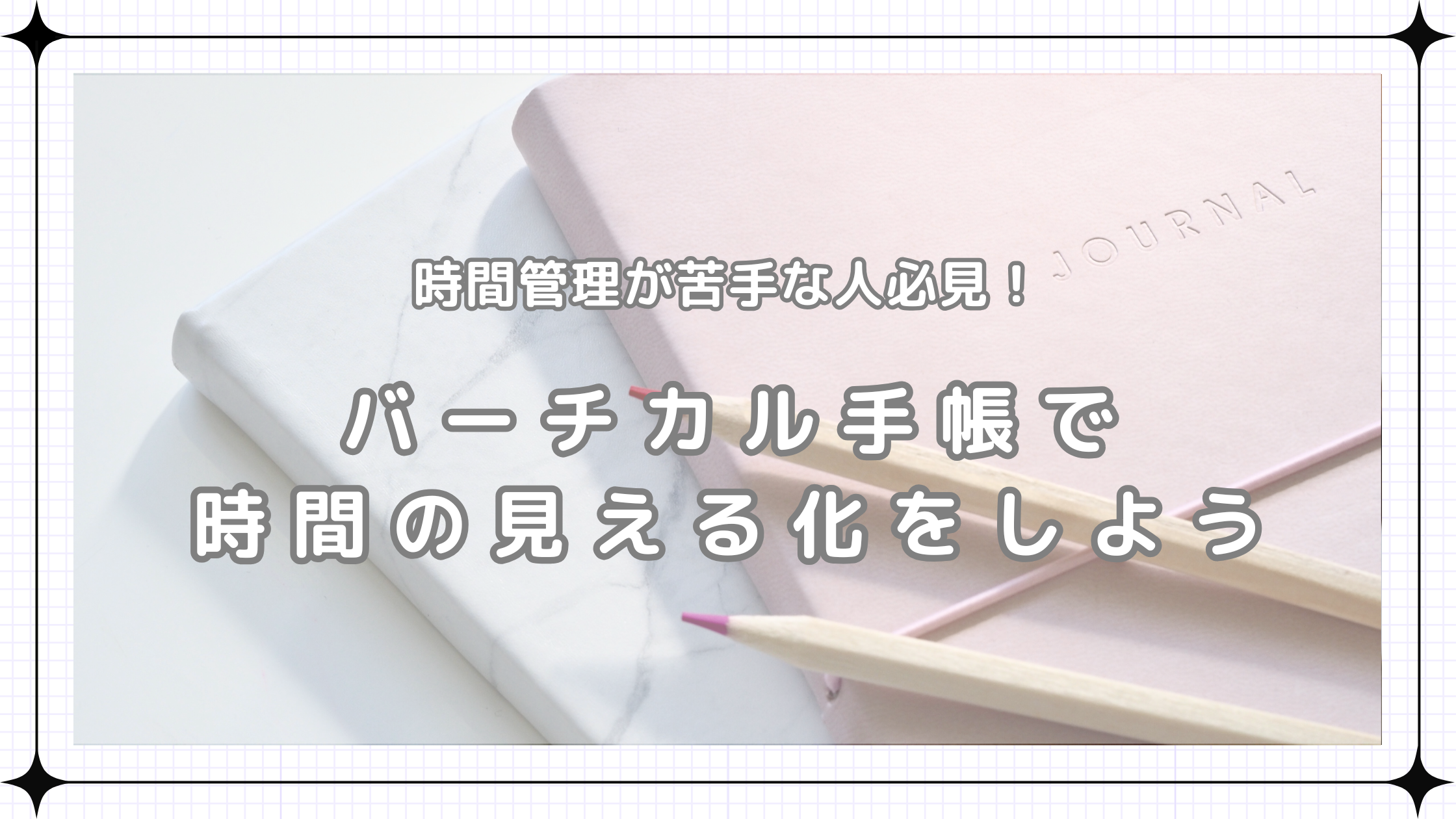
コメント